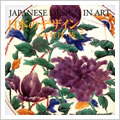大寒に入ってからはますます寒さが厳しくなってきている。このようなことは十数年来なかったように記憶している。私の工房では、紅花染を毎日のように行なっていて、「寒の紅」といわれているように、この寒さが逆にありがたく、今年は鮮やかな色に染まっている。
紅花染は単独で色を濃く染めていく、いわゆる韓紅色 (からくれないいろ) が、王朝の女人たちに愛されていたが、その一方で支子 (くちなし) などの黄色をあらかじめかけておいて、その上に紅花を染めて、朱がかった色にすることも行われた。黄丹 (おうに/おうだん) というような色名で知られ、高位の人に着用されていた。
江戸時代になると、支子に代わって鬱金 (うこん) が、大航海時代の波に乗って日本へ将来されるようになり、鹿児島あたりなどの温暖な地で栽培さるようになった。それ以後、染料としてよく用いられるようになって、あらかじめ鬱金で鮮烈な黄色にしてから紅花をかけあわせる「紅鬱金」が染められるようになった。
とりわけ江戸時代の中頃をすぎる頃より、黒や茶地に小紋染あるいは縞、格子といった地味な着物が流行するようになると、表とは逆に、裏には派手な「紅鬱金」の絹を付けた。まさに裏勝りにして楽しんだのである。
紅花は血行をよくする薬としても知られていて、肌にそれが付いていると、血のめぐりがよくなるとも言われていたからでもある。
 韓紅、黄丹、紅鬱金の色標本と詳しい解説は
韓紅、黄丹、紅鬱金の色標本と詳しい解説は
『日本の色辞典』をご覧ください。
吉岡幸雄・著 (紫紅社刊)