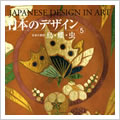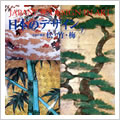今年は何十年ぶりか、紅葉の彩りが美しかったと言われている。
京都もいつもより2週間ほど早く色づき、私も久しぶりに麗しい黄や紅の葉のかさなりを観たようだった。11月11日から大分県竹田市へ出かけたが、九重連峰の秋色も存分に味わうことができた。
とくに、滝廉太郎の「荒城の月」で知られる岡城の紅葉は、まさに時にあっていて、感動的な紅葉の襲を観たようだった。
12月に入って、今日大学へ通う道すがら、叡山電鉄の車窓から比叡山をながめていたが、色を失って、松や杉の常緑樹のいわゆる常磐の色になっていた。
このところ毎日のように時雨があって、時には北の方では白いものが舞っているようだ。
昨日、12月7日、客人と一緒に西山、大原野の花の寺 (勝持寺) と大原野神社へ行ってきた。紅葉はすでに散っていて、参道のわきや庭には、人がまるで敷きつめたように、枯紅葉がかさなりあっていた。
大原野神社にはまだこの紅葉がかなり枝ににこっていて、常磐の森を背景にわずかながら初冬のにぶい光のなかで、紅と黄色が飛び散ったように彩りを添えていた。
 『京・四季のうつろい』
『京・四季のうつろい』
岡田克敏 写真集 (紫紅社刊)
洛中洛外の細やかな風景美を愛し、永きにわたって歩きつづけ、撮りつづけた一写真家の、心をとらえた一瞬の自然の美。京都を愛する人への贈り物にもどうぞ。